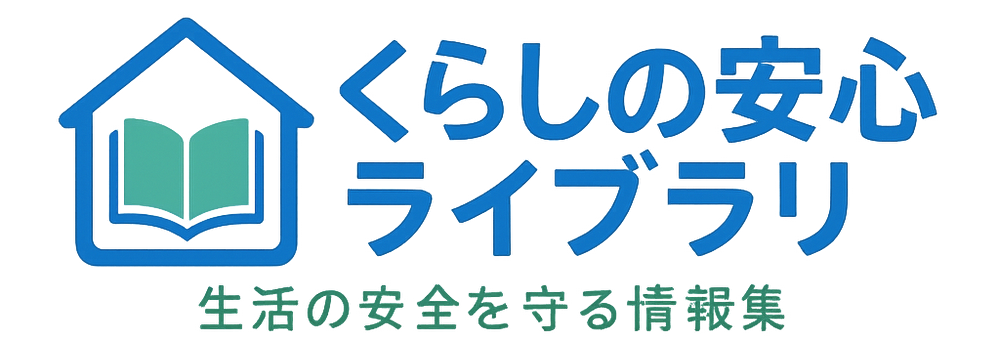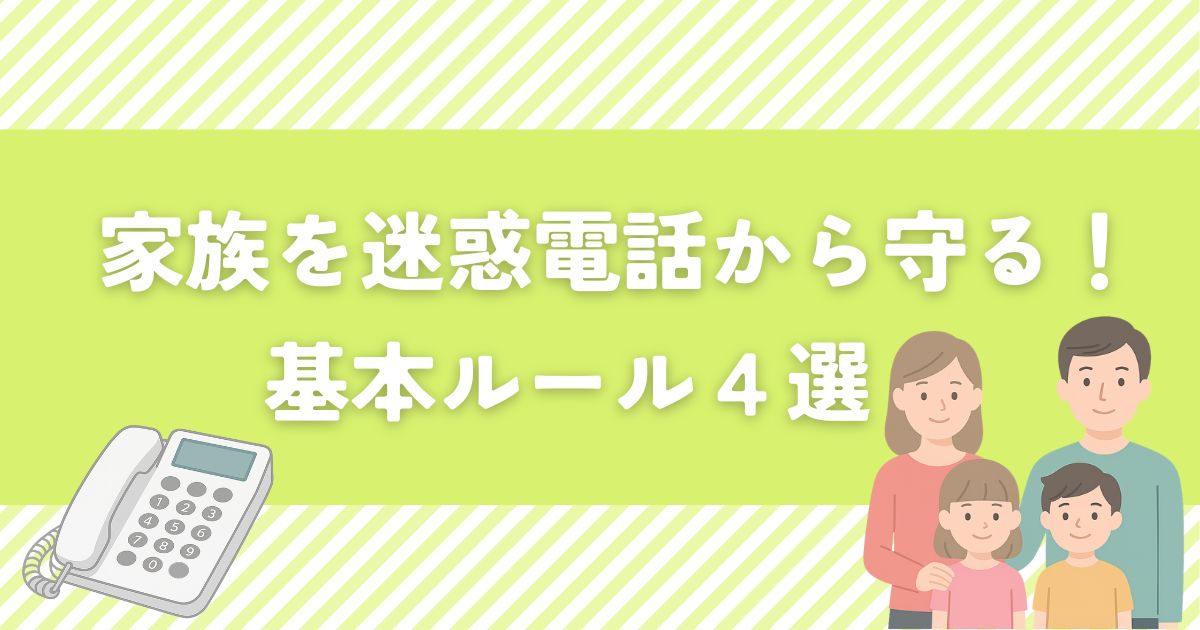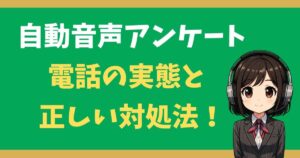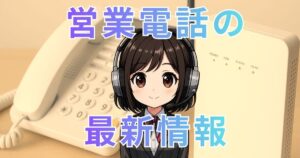最近は、固定電話やスマートフォンにかかってくる迷惑電話や不審な勧誘が増えています。
特に、高齢のご家族や子どもがいる家庭では「電話に出てしまったらどうしよう」と不安に感じることもあるでしょう。
そこで今回は、家族を守るために知っておきたい迷惑電話対策の基本ルールをまとめました。
1.「知らない電話に出ない」という習慣を共有する
迷惑電話対策の第一歩は「知らない番号には出ない」というシンプルなルールです。
実は、知らない番号の電話に出ることは、複数の
自分だけでなく、家族全員が徹底することで被害を大きく減らせます。
特に注意したいのが、高齢者や留守番をしている「子ども」。
相手の言葉を疑うことなく、家族や友達の個人情報を聞かれるまま正直に伝えてしまう可能性があるためです。
これを防ぐには、家族であらかじめ「知らない番号からの電話には出ないでね」と約束しておくことが大切です。
また、高齢者の方の場合「電話が鳴るとつい反応してしまう」というケースはかなり多いため、「電話に出ないことが身を守ることに繫がる」という内容をしっかり伝えておきましょう。
2.「着信拒否」や「迷惑電話対策」の機能を活用
スマートフォンには、不審な番号をブロックできる機能が標準で備わっています。
また、アプリを利用すれば、迷惑電話として報告されている番号を事前に判別できるものもあります。
固定電話の場合も、近年は「通話前に相手に名乗ってもらう」「録音を通知する」などの迷惑防止機能が付いた機種が増えています。
こうした機能を積極的に活用することで、家族の不安を軽減できます。
もし機能が不足している場合は、外付けの「迷惑電話防止機器」を導入するのも安心です。
3.不安を感じたら必ず家族に相談する
万が一、家族の誰かが不審な電話に出てしまった場合でも、すぐに家族に相談できれば被害を防げる可能性が高まります。
「よく分からない電話がかかってきたら、必ず家族に相談しよう」とルール化しておくことが大切です。
特に高齢のご家族は「迷惑をかけたくない」と思って黙ってしまうケースもあるため、日頃から「何かあれば気軽に相談してね」と声をかけておくと安心です。
公的機関や相談窓口を知っておく
迷惑電話が続いたり、不安な内容だった場合には、公的な相談窓口を活用しましょう。
- 消費生活センター(188):迷惑電話やしつこい勧誘に関する相談の受付
- 警察相談専用電話(#9110):詐欺の可能性がある場合や、被害を受けたときの相談窓口
家族みんなで「困ったときはここに相談できる」と共有しておくだけでも心強いものです。
特に消費生活センターは、商品の購入やサービスの契約で困った場合に頼りになる身近な機関となりますので「困ったことがあったら、188(イヤヤ)にダイヤルしよう」と家族みんなで覚えておきましょう。
消費生活センターへの相談については、当サイト内にある以下の記事で詳しくお伝えしていますので、そちらも参考にして頂けると幸いです。
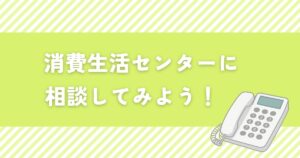
まとめ:家族みんなで4つのルールを徹底しよう!
迷惑電話対策は、一人だけで取り組むよりも「家族全員でルールを共有し、それらを守る」ことが重要です。
- 知らない番号には出ない
- スマホや固定電話の機能でブロックする
- 不安を感じたら必ず家族に相談する
- 必要に応じて公的機関に連絡する
これら4つのルールを徹底することで、大切な家族を迷惑電話のストレスやリスクから守ることができます。
「うちは大丈夫」と油断せず、日頃から家族のメンバー同士でコミュニケーションを取り、対策を共有することで「安心できる暮らしの実現」を目指しましょう。