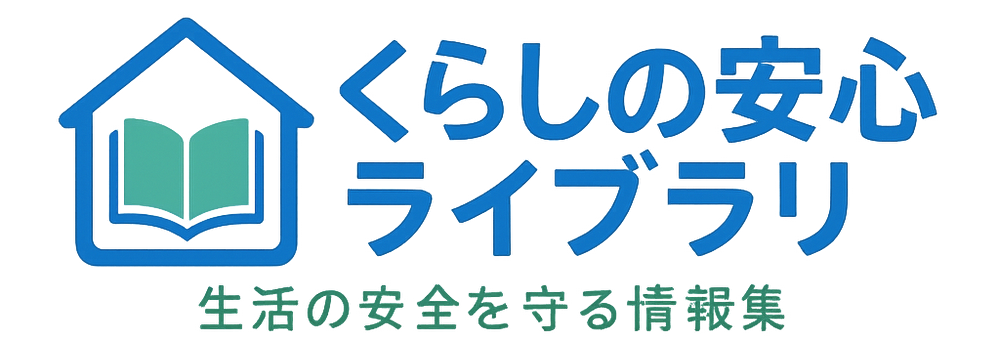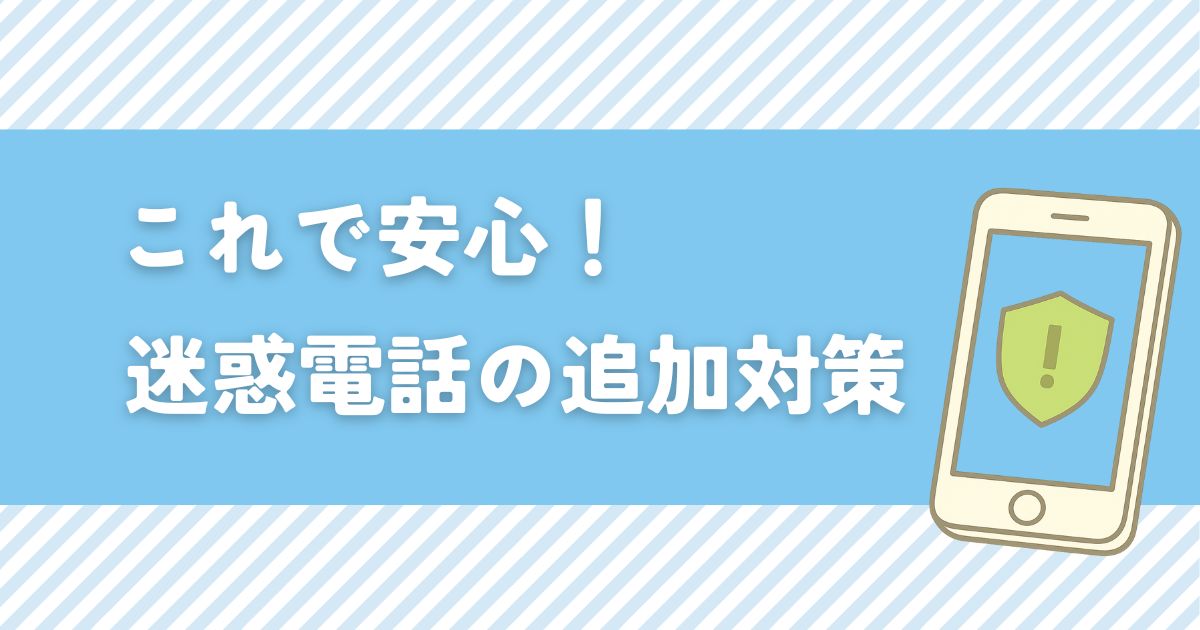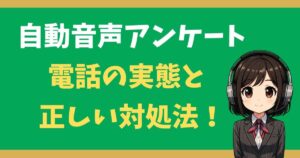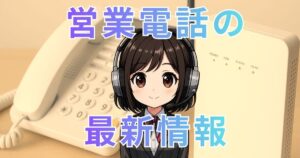スマートフォンや固定電話に備わっている「着信拒否機能」は、迷惑電話対策の基本的な手段の一つです。
しかし、実際には着信拒否だけでは十分に防ぎきれないケースもあります。
ここでは、その理由と、さらに安心できるための追加対策について解説します。
着信拒否だけでは防ぎきれない理由
新しい番号からかかってくる
営業電話や詐欺電話を行う業者は、複数の番号を使い分けて発信することがよくあります。
一つの番号をブロックしても、別の番号からかかってくるため、いたちごっこになってしまうのです。
非通知や公衆電話を利用される
非通知設定や公衆電話を利用して発信してくるケースもあります。
この場合、特定の番号を拒否しても意味がなく、着信拒否機能だけでは限界があります。
家族や大切な連絡を見逃すリスク
着信拒否を強くかけすぎると、重要な連絡までブロックしてしまう可能性があります。
たとえば、宅配業者や学校からの電話が拒否されると不便になるため、単純に拒否するだけでは安心につながらない場合があります。
追加でできる対策
キャリアの迷惑電話サービスを利用する
NTTドコモ、au、ソフトバンクなど主要キャリアでは、迷惑電話や詐欺電話を自動的に判別して警告してくれるサービスを提供しています。
着信時に「迷惑電話の可能性があります」と表示されるため、事前に判断がしやすくなります。
有料オプションになることもありますが、安心感を大きく高められる方法です。
専用アプリで警告表示
スマートフォン向けのアプリには、着信番号を判別して警告してくれるものがあります。
「電話帳ナビ」や「Whoscall」などのアプリを利用すると、過去に迷惑電話として報告された番号を事前に知ることができます。
これにより、出るべき電話かどうかを判断しやすくなります。
固定電話の迷惑防止機能を活用
固定電話には「通話録音のお知らせ」や「名前を名乗らないとつながらない」などの迷惑防止機能が付いている機種があります。
高齢者世帯では特に有効で、怪しい相手を自動的に振り分ける効果があります。
家族でルールを決める
技術的な対策だけでなく、家族間で「知らない番号には出ない」「怪しい電話はすぐ切る」といったルールを共有することも重要です。
特に高齢の家族がいる場合、被害に遭わないための共通ルールを決めておくと安心です。
公的機関や相談窓口を活用する
迷惑電話があまりにしつこい場合は、消費生活センター(電話188)や警察相談専用電話(#9110)に相談することもできます。
また、地域によっては自治体が高齢者向けに「迷惑電話防止機器」を貸し出しているケースもあります。
公的なサポートを積極的に利用することで、被害を防ぐ確率がさらに高まります。
まとめ:複数の方法を組み合わせて安心を高める
着信拒否設定は基本的な対策ですが、それだけでは限界があります。
例えば、複数の番号や非通知を利用されると、着信拒否をしていても突破されてしまいます。
また、大切な電話まで拒否してしまう可能性があるため、少々困りものでした。
キャリアサービスや専用アプリを併用すると効果的
家族でルールを決めることで被害を防げる
公的機関の相談窓口も積極的に活用する
これらを組み合わせて対策することで、より安心して電話を利用できるようになります。
「着信拒否だけでは不安」と感じる方は、ぜひ複数の方法を取り入れてみてください。