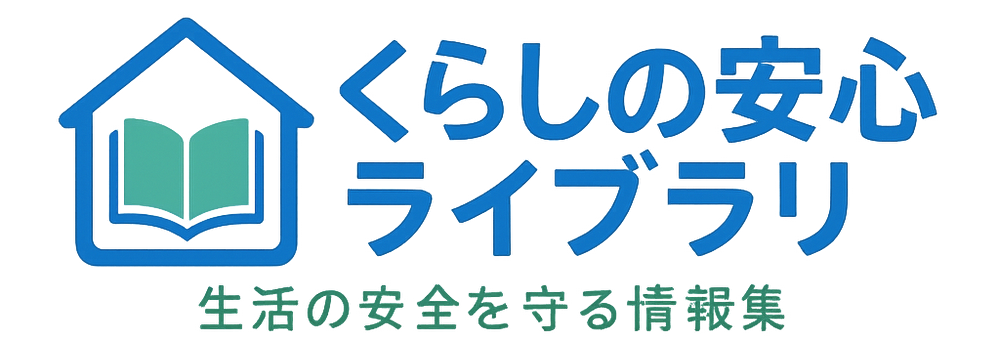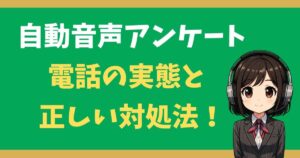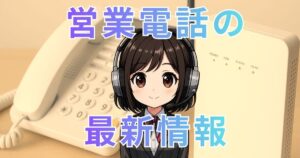知らない番号からの営業電話。
「無料で広告掲載できます」
「電話料金が安くなります」
そんな誘いに戸惑った経験はありませんか?
実は、個人事業主やオフィスへの営業電話は、
消費者保護法やクーリングオフ制度の対象外になることが多いのです。
そのため、安易に契約すると後から取り消すのが極めて困難。
本記事では、対象外となる理由や、実際のトラブル事例、
そして営業電話を防ぐための具体的な対策を解説します。
消費者保護法・クーリングオフ制度の基本
クーリングオフ制度は、
「訪問販売」や「電話勧誘販売」などで契約した消費者を守るための仕組みです。
契約後でも一定期間内(8日〜20日以内)であれば、
理由を問わずに契約を解除できるという制度。
しかしこの制度は、
「生活のために契約を結ぶ一般消費者」が対象です。
つまり、「仕事目的」や「事業目的」で契約した場合は、
原則としてクーリングオフが適用されません。
対象外になるケースとその理由
事業者や個人事業主が契約を結ぶ際、
次のような条件に当てはまると「事業目的」とみなされます。
- 契約書・請求書の名義が屋号や事業名義の場合
- 契約内容が業務用機器・オフィス設備に関するもの
- 広告掲載・回線契約など、明らかに事業活動を目的とする内容
営業電話の多くは、最初に
「会社の担当者様ですか?」
「オフィスの方でしょうか?」
と確認してくるのはこのためです。
一度「事業者」と認定されると、
消費者契約法の適用範囲外となり、契約解除のハードルが高くなります。
よくある被害・トラブル事例
事業者向け営業電話では、
次のようなトラブルが頻発しています。
- SEO対策やホームページ制作の高額契約を電話一本で結ばされる
- 「無料」と言われて申し込んだら、実は年間契約だった
- ビジネス回線や複合機のリース契約が自動更新され、解約できない
さらに悪質なケースでは、
「電話口で了承した=口頭契約成立」とされ、
書面が届く前に契約が成立したと主張されることもあります。
このような被害は、クーリングオフできないため、
泣き寝入りする事業者が後を絶ちません。
営業電話を防ぐための事前対策
被害を防ぐには、日頃から次のような対応を徹底しましょう。
- 相手の会社名・担当者名・用件を必ず確認
- 「録音しています」と一言伝える
- その場で契約・了承は絶対にしない
- 不明な電話番号はネット検索で確認
- 着信拒否や自動録音アプリ(Whoscall・スマート留守電など)を活用
例えば、電話口で流す、たった一言の
「録音しています」という音声で、
トーンが落ちる業者も少なくありません。
営業電話は相手のペースに乗らないことが最大の防御です。
契約してしまった後の対処法
もし契約してしまった場合も、
次のような手段でトラブルを軽減できる可能性があります。
- 「不実告知」や「誤認による契約」であれば無効を主張できる場合あり
- 内容証明郵便で解約を申し入れる
- 商工会議所・弁護士・中小企業庁の相談窓口へ相談
事業者であっても、
不当勧誘や虚偽説明があった場合は救済を受けられる可能性があります。
焦らず、契約書・録音・メールの記録など、
証拠を保全して専門機関へ相談しましょう。
相談できる公的窓口一覧
| 相談窓口名 | 相談内容・対応範囲 |
|---|---|
| 中小企業庁・取引相談窓口 | 取引トラブル全般に対応。リース契約・広告契約・業務委託などの相談が可能です。 |
| 国民生活センター(事業者相談) | 「事業者間トラブル」としての相談を受付。悪質な勧誘に関する情報も共有できます。 |
| 弁護士会・法テラス | 契約書の内容確認や解除方法など、法的観点からアドバイスを受けられます。 |
まとめ:事業者は「守られない前提」で自衛を
個人事業主・オフィス・法人は、
一般消費者とは異なり、法律の保護が限定的です。
そのため、
「軽い気持ちで了承した」
「無料と言われたから受けた」
といった対応が、高額なトラブルに直結することもあります。
営業電話がかかってきたら、
すぐに答えず、必ず情報を調べてから判断しましょう。
録音・拒否・確認。
この3つを徹底することが、事業者を守る最も確実な手段です。